
暮らしに明かりを照らす、家づくり。親松の「あかがわ建築設計室」。
プロモーション | その他
2025.10.21
家を建てることは、人生におけるひとつの節目。中央区親松にある「あかがわ建築設計室」では、住む人の暮らしを大切にした家づくりを提案しています。今回は事務所にお邪魔して、赤川さんご夫婦に建築を仕事にしたきっかけから、家づくりについていろいろとお話を聞いてきました。

あかがわ建築設計室
赤川 仁一 Jinichi Akagawa
1982年新潟市出身。神奈川大学で建築を学んだ後、新潟に戻り複数の建築事務所で働く。一級建築士の資格を取得し、2017年に「あかがわ建築設計室」を立ち上げる。

あかがわ建築設計室
赤川 聖子 Seiko Akagawa
1981年阿賀野市出身。工学院大学を卒業後、新潟に戻り、複数の建築事務所で働く。一級建築士の資格を取得後、仁一さんの独立の準備を手伝う。現在は4歳の双子の子育てと仕事に奮闘中。
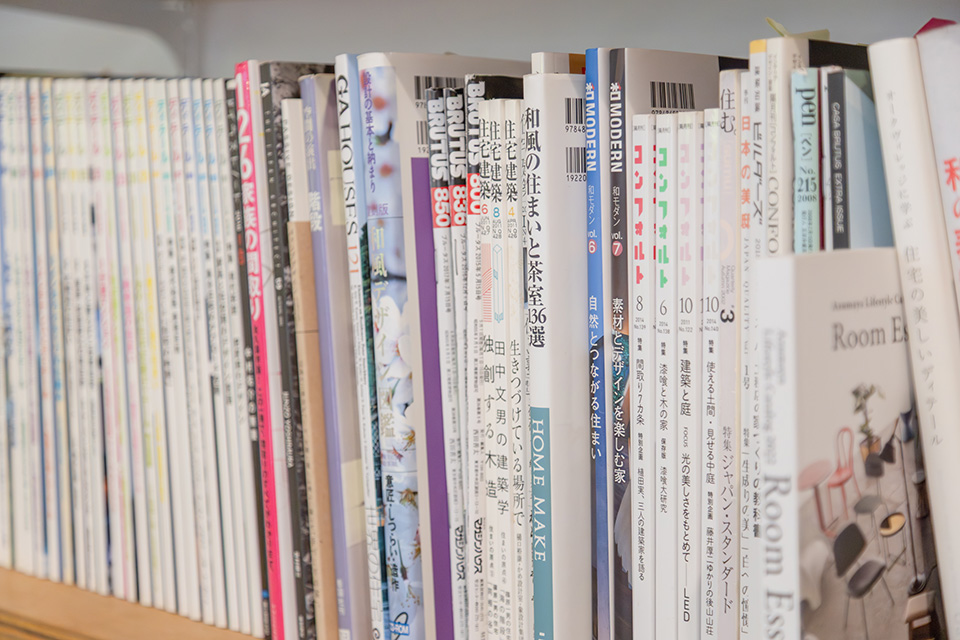
独立の決め手は、最善の提案ができること。
——今日はよろしくお願いします。おふたりはそれぞれ別の大学で建築を学ばれたんですね。
仁一さん:子どもの頃から、工作の授業やプラモデルを組み立てるのが好きだったんです。高校で理系に進んで、その先で何を勉強したいか考えていたとき、ふと建築が思い浮かんで。「じゃあ、やってみよう」と思って建築の道に進むことにしました。
聖子さん:私も昔から絵を買いたり、手を動かして何かをつくることが好きでした。私も高校では理系に進んで、建築に興味があったのでこの道を選びました。
——建築っていうと、大きな建物を設計される方もいますよね。
仁一さん:大学では建築の歴史や、体育館や保育施設などの大きな施設をテーマにした課題が多かったんですけど、それより僕は身近な暮らしを支える住宅に興味があって。大学を卒業した後は、新潟市内の建築事務所で働きはじめました。
聖子さん:私も大きなアトリエに務めてコンペに出すような建築をつくるよりは、生活に密着した住宅をつくりたいって思っていて。東京より新潟のほうが、家づくりの自由度がありそうと思って新潟に帰ってきました。

——大学を卒業後、おふたりは同じ事務所で働いていたと聞きました。
仁一さん:最初に働きはじめた会社が同じでした。そこの社長は、大学の教授みたいな人で。入りたての僕たちに自分の持っているものを教えてくれたり、「こういうことをやってみなよ」って言ってくれたりするような人でした。でも、僕らはまだ経験が浅かったので、どうしたらいいのかわからなかったんです。わからないまま、現場に出て、怒られて、夜遅くまで働いて……みたいな感じで、必死に働きながら仕事を覚えていきました。
——けっこう過酷な社会人1年目だったんですね。
仁一さん:その後いくつかの事務所で働いてみて、当たり前なんですが、それぞれの考え方や進め方が全然違うことに気づきました。技術を大事にするところもあれば、コストを重視するところもあって。仕事にも慣れて、お客さんに提案できるようになると今度は、自分が本当に良いと思う提案であっても必ず採用されるわけではない、ということも知りました。
聖子さん:そうそう、お客さまにとってベストだと思っても、会社の意向にあっていないと提案が通らなかったんです。いくら自分が良いと思った提案でも「社長はなんて言っていた?」って聞かれてしまうこともあって。社長との間に入って、伝言を伝えるだけの存在になっているような気がしていました。

——自分自身の提案が思うようにできない、と。
仁一さん:会社に勤め続けるのも、ひとつの手だとは思ったんですけど、提案自体の良し悪し以外で決定してしまうことにモヤモヤしてしまって。奥さんとも「自分だったら、もっとこうできるのに」ってよく話していて。「依頼してくれるお客さまのために仕事がしたい」という思いが強くなっていきました。その後、奥さんの協力もあって一級建築士の資格を取ることができて、2017年に「あかがわ建築設計室」を立ち上げました。
暮らしを一緒に考える、「あかがわ建築設計室」の家づくり。
——「あかがわ建築設計室」では、「暮らしをそっと照らす住まい」を提案しています。
仁一さん:家というよりは、その人の暮らしを一緒につくっていきたいと思っています。完成した家に明かりが灯った瞬間、「家に命が宿った」と感じるんです。そこに住む人の暮らしを、そっと支えられるような住まいをつくりたい、という思いを込めています。

——具体的には、どんな住まいを?
仁一さん:お客さまがどんな暮らしをしたいのか、暮らしの中で何を大切にしているかを聞いてから、家を提案しています。だから、僕たちがつくる家は、デザインや性能を売りにしていなくて。お客さまの暮らしの延長線上にある住まいを提案したいので、お客さまのしたい暮らしに合わせて部屋数や間取りを決めています。
——その考え、もう少し詳しく聞かせてください。
仁一さん:デザインや性能が良いことに越したことはないんです。でも、それだけが家づくりの正解ではないと思っています。性能を求めすぎて、本来の予算を超えてしまったとき、家を建てた後の暮らしに無理が生じてしまうなら本末転倒です。お客さまの予算の中で、最善の暮らしを提案することが、僕たちの仕事かなって。
聖子さん:性能を100点にするために無理をするより、70点くらいにして、自分らしく暮らせたほうが生活は豊かになると思うんです。私たちにお願いしてくれる人が、どうしたら喜んでくれるかを、たくさん考えて提案しています。

——こちらで建てられた家には「帰要の家」や「奏郭の家」というように、それぞれ名前がついています。
仁一さん:大きな会社さんだと、同じ間取りで家をつくるところもありますが、僕たちはお客さまの暮らしを想像しながら家づくりをしています。その家を「A棟」「B棟」って読んでしまうのは味気がないなと思って。家も家族の一員のような存在だと思うので、ひとつひとつ名前をつけてあげたくてはじめました。
——家も家族の一員……なんだかあたたかい気持になりますね。
仁一さん:その土地やお客さんの雰囲気から、一文字ずつ意味を考えて、漢字で名前をつけています。最初は続けるつもりはなかったんです。でも、「うちの家はどんな名前になるんですか?」って楽しみにしてくださる方が多くて。毎回考えるのは大変ですが(笑)、お客さまが喜んでくださるので続いています。

誰かのためになる仕事を、これからも。
——「そっと暮らしを照らす住まい」を提案するなかで、大切にしていることはありますか?
仁一さん:建築家のミース・ファン・デル・ローエの言葉で「less is more」という言葉があって。「より少ないことは、より豊かなこと」という意味なんです。僕たちはこれを、ただシンプルにすればいいということではなく、「必要なものを見極めて、ちゃんと残していく」っていう意味と捉えています。
——ふむふむ。
仁一さん:家づくりをする中で機能やデザインを足そうと思えば、いくらでも足せるんです。でも、予算や空間の中で、本当に必要なものだけを選んでつくった家がいちばんいいと思っていて。住まいはお客さまが暮らして、はじめて完成します。お客さまの暮らしを刻んでいけるような、余白のある住まいが理想なんじゃないかなって。

——家を建てたら完成、というわけではないんですね。
聖子さん:家づくりの時間そのものも、お客さまに楽しんでもらいたいですね。住まいが完成するまでの打ち合わせは、お客さまにとって大変だと感じるかもしれませんが、「話していくうちに、この家で暮らすイメージが見えてきた」って言ってもらえるような、丁寧な関係づくりを大切にしています。
——最後に、「あかがわ建築設計室」のこれからの目標を教えてください。
仁一さん:まずは目の前の仕事を丁寧にやっていこうと思います。その中で同じことを繰り返すのではなく、少しずつ進化できたらいいな、と。あとは、お客さまだけではなく、家づくりに関わる職人さんとの関係性も大事にしていきたくて。彼らが気持ちよく働ける環境もつくっていきたいですね。これからも関わるすべての人に感謝しながら、お客さまに寄り添った家づくりをしていこうと思います。

あかがわ建築設計室
新潟市中央区親松11-9
Advertisement
関連記事
その他
上古町にオープンした「古道具屋MARBLE」で、素敵な家具や雑貨と出会う。
2023.08.16

その他
自ら手を動かし、プロジェクトをサポートする「IDEKO」の小出さん。
2024.11.01

その他
デザインで地域の価値をつないでいく。「潟マルシェ」を運営する松浦さん。
2024.08.19

その他
スケボー×福祉がコンセプトの「VIVID SKATE SCHOOL」。
2020.11.29

その他
着物を普段着のように着て欲しい。「レンタルきもの屋まゆ」の取り組み。
2021.02.24

その他
納屋で花や植物、陶器やアンティーク家具を販売する「土と花 花筏」。
2023.10.10















